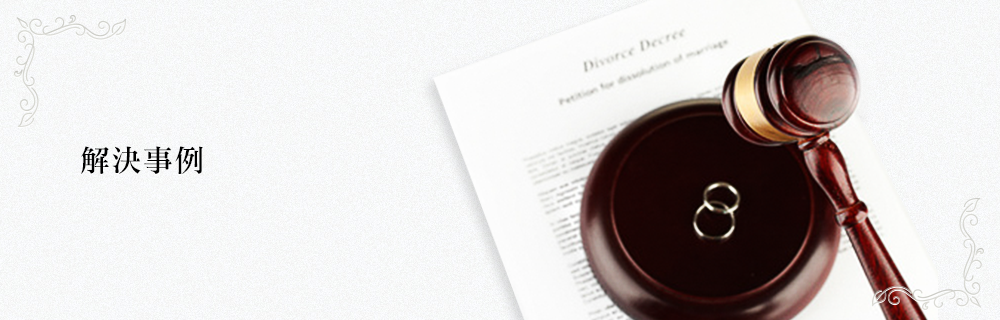
離婚に消極的な夫に対して離婚調停を申し立て、財産分与約160万円を夫から取得して離婚した事例
依頼者 妻
夫 40歳 公務員 大阪府豊中市在住
妻 35歳 主婦 大阪府豊中市在住
離婚原因 浪費、性格の不一致
きっかけ 夫が離婚に応じてくれない
財産 不動産、預貯金、退職金、自動車
子ども 1人
Aさんは、家事育児を手伝わず、お金の使い道に関する意見も合わない夫Bと夫婦喧嘩が絶えなくなり、離婚を希望するようになりました。
当初、Aさんは自分で夫Bに離婚を求めましたが、夫Bは「離婚したくない」と繰り返すだけで、離婚に応じることはありませんでした。
そのため、Aさんは夫Bとの別居を決意し、別居後の夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士が夫Bに対して離婚協議と婚姻費用の支払を求めたところ、夫Bも弁護士に依頼しました。
ただ、その後も夫Bは「離婚については気持ちが揺れている」などの主張を繰り返してきたため、一向に離婚協議が進展せず、夫Bからは婚姻費用も支払われませんでした。
そこで、弁護士は離婚調停と婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てました。
調停になると、夫Bは、離婚自体は強く争わなくなりましたが、面会交流調停を申し立ててきたため、調停手続きでは①婚姻費用・②財産分与・③養育費・④面会交流が主たる争点となりました。
①婚姻費用については、算定表どおりに夫BがAさんに対して月額13万円の婚姻費用を支払う内容で合意しました。
②財産分与について、夫Bは預貯金口座の資料は開示してきましたが、当初退職金や退職年金の資料を開示しませんでした。
そのため、弁護士は、裁判官の意見を求めたり、調停委員を通じて粘り強く夫Bに退職金等の資料の開示を求め続けました。
その結果、夫Bは退職金と退職年金の資料も開示しました。
その後、不動産の評価額についてAさんと夫Bで主張額が異なったものの、それ以外は概ね客観的な財産資料を基に算定することに争いがなかったため、最終的にAさんと夫Bの主張する財産分与額の間をとる形で合意しました。
具体的には、夫BがAさんに対して財産分与金約160万円を支払う内容で合意しました。
③養育費については、Aさんが調停の途中で就職したという事情があったため、Aさんの就職後の給与明細の金額を前提にAさんの年収を算定し、「養育費を月8万円とする」という提案が調停委員会から出されました。
これに対し、夫Bは「Aさんには今後賞与も支払われるはずなので、Aさんの年収はもっと高いはずだ」「養育費は月7万5000円にすべきだ」などと主張してきました。
ただ、その一方で、夫Bは年収が毎年上がっているにもかかわらず、前年の年収資料しか開示していませんでした。
そこで、弁護士は「Aさんの今年の実際の年収を基に養育費を算定するのであれば、当然夫Bの年収も前年のものではなく今年の年収を前提とする必要がある。その場合、養育費の金額は月8万円よりも更に高くなる可能性もある。」などと反論し、夫Bの今年分の給与明細や賞与明細の開示を求めました。
その結果、夫Bは上記主張を断念し、養育費を月8万円とすることを認めました。
そのため、夫BがAさんに対して月8万円の養育費を支払う内容で合意しました。
④面会交流について、Aさんは面会交流自体を拒否する意向は持っていませんでしたが、「離婚後に開始したい」という意向を持っていました。
そこで、弁護士は、Aさんの意向を前提に夫Bと協議し、最終的に「離婚後に毎月1回面会交流を実施する」という内容で合意しました。
そのため、最終的に上記①~④の内容で離婚が成立しました。
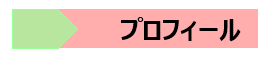
 寺尾 浩(てらお ひろし)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】